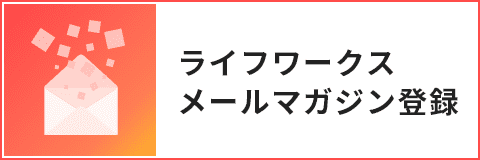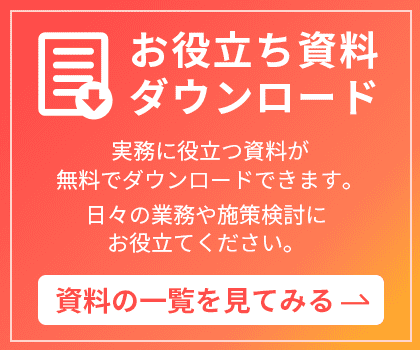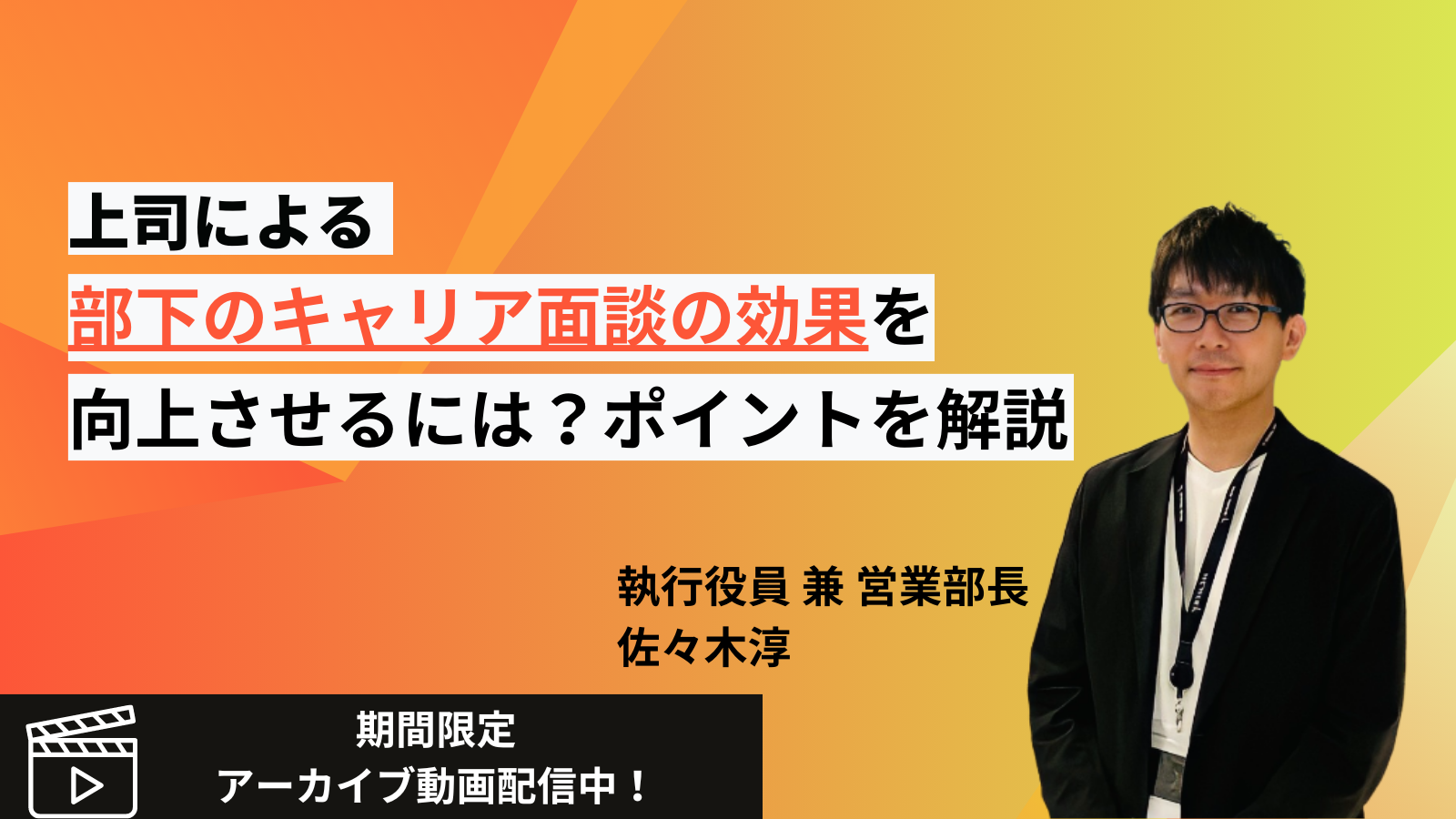同一労働同一賃金とキャリア
私たちが自律的に働き続けるためには、様々な社会の仕組みや制度の影響を少なからず受けるのではないでしょうか。そこで、今回のコラムは、今日の私たちの働く環境を考える上で重要なテーマの一つとなっている同一労働同一賃金とキャリアの関係について、株式会社日本総合研究所 理事/主席研究員の山田久氏より寄稿いただきました。

安倍政権が「同一労働同一賃金」を政策の目玉の一つにしてから、この馴染のない専門用語が巷間でも聞かれるようになったが、その正確な意味合いを理解している人は必ずしも多くないのが実情ではないか。しかし、わが国人口動態の変化から考えれば、それは今後の働き方の巡るキーワードとなり、実は働く人々のキャリア形成にとっても大きな影響を及ぼしていくことになると考えられる。そこで本稿では、まず、「同一労働同一賃金」がどのようなものかを解説したうえで、それが働く人々のキャリア形成にとって、どのような意味を持つかについて考えたい。
導入が目指されるのは「日本型」
安倍政権は働き方改革を優先政策課題に位置付け、その一つの柱に「同一労働同一賃金の実現」を位置づけてきた。こうした政府の動きの背景には、成長と分配のリンケージによって経済の好循環を形成するカギとなる賃金の引き上げが、思うような成果をあげていないことがある。政労使会議や官民対話によって産業界に賃上げを要請してきたが、その限界が見えてきた。そうした状況下、非正規労働者の処遇改善が置き去りにされてきたことに改めて焦点を当て、最低賃金の引き上げと両輪で、賃金の底上げを行うロジックとして、同一労働同一賃金というコンセプトに白羽の矢が当たった形である。
だが、同一労働同一賃金というのは癖玉である。なぜなら、その本家である欧州とわが国の雇用慣行・賃金決定の仕組みが大きく異なるからである。そもそも欧州における同一労働同一賃金への取り組みは、男女格差の是正に代表されるダイバーシティーの観点から始まったものである*1。それは、人権保障に関わる概念であり、差別禁止規制が基本である。その延長線上に、雇用形態による格差に対する「合理的理由のない格差禁止」が規定された。それが可能なのは、欧州の雇用・賃金制度は「まず仕事ありき」の仕事基準に則っており、同じ仕事であれば誰がその仕事に就いていようと同じ賃金をつける、というのがやり易い土壌がある。より具体的には、欧州での賃金決定は産業別に組成された組合と使用者団体との交渉により、職種別の習熟度別の賃金相場が決められる。さらにそれは、拡張適用という仕組みによって、組合員のみならず全労働者に適用される仕組みがある。この結果、就業形態や属性が異なっても、職種とその習熟度が決まれば基本的には同じ賃金が適用されることになっているわけだ。
これに対し、わが国の雇用・賃金制度は「まず人ありき」の人基準に則っており、総合職か一般職か、嘱託社員かパート社員か、はたまた派遣社員かによって賃金が大きく異なる。かつては役割自体が異なったため賃金が異なったことに合理性があったわけだが、人件費削減が至上命題とされてきた過去4半世紀のうちに、それぞれが行う仕事がオーバーラップするケースが増えてきた。つまり、正社員と非正規社員の仕事内容が似てきたのに、賃金格差だけが大きいケースが目についてきたわけである。そこで両者の賃金格差を是正すべきという声が強くなっていたが、正社員賃金は企業別の労使交渉によって決まる一方、非正規賃金はそのときの労働需給を反映して決まるため、両者は基本的に連動しない。欧州とは賃金決定の仕組みが大きく異なるわけで、原理的には同一労働同一賃金が成り立つ環境にはない、といえる。
そこで、今回のわが国の同一労働同一賃金は、わが国の雇用・賃金の仕組みに配慮した、あくまで「日本型」での導入を目指すべきである。欧州の文脈での本来の同一労働同一賃金は、就業形態のみならず属性での賃金差を是正しようというものであり、それは社会横断的に、正社員間の格差も含めて合理的な説明ができない差はなくす、というものである。これに対し、今回のわが国では「正規・非正規間の、あくまで企業内での、不合理な処遇格差の是正を目指す」ということになっている。さらに、新たなルールの導入による現場の混乱を抑えるべく、具体的な事例を含むガイドラインが示されることになっている。すでに公表された案では、手当や賞与については踏み込んだ内容になっているが、賃金制度の根幹である基本給部分については、企業が説明責任を果たせばこれまでの人基準の賃金制度は許容されることが示されている。
人口動態変化からみればいずれは本来の文脈が重要に
このように、今回の同一労働同一賃金の導入は「日本型」であり、欧米の「ダイバーシティー」の実現という文脈とは異なるが、わが国の人口動態を勘案すれば、いずれはその本来の文脈での導入が必要になるだろう。
わが国の人口はすでに減少局面に入り、今後そのトレンドが加速していくが、労働力の面から企業にとりわけ大きな影響が及ぶのは、従来コア労働力として位置づけてきた男性現役世代が急激に細っていくことを通じてである。このタイプの労働力は、過去15年(2000→2015年)ですでに270万人減少しているが、今後15年(2015→2030年)で410万人減少するのである*2 。もはや女性、そしてシニアに重要戦力として活躍してもらわなければ、企業活動は成り立たない。人口問題への対応を念頭に置いたうえで女性が男性と対等に活躍するには、定時退社を基本にして、男性も家事や子育てをシェアすることが必要になる。
そうしたなかで衝撃的なのは、今後20年先を展望した場合、大手企業を中心に「セミリタイア」になる50歳代後半以降の就業者の働き手全体に占める割合が、4割近くに達する見通しであることだ。そうした状況では定時退社を基本にした業務運営体制を整備しなければ、シニアが体力的に働けず、現役世代への負荷と不公平感が限界に達するだろう。これが、今回の働き方改革のもう一つの柱である「残業削減」が目指す本来の意義である。そして、多様な属性の人々が働くようになれば、職務と勤務地が無限定で長時間労働が当たり前の「日本型正社員」以外の働き方が多様にならざるを得ず、それぞれが戦力として十分に活躍してもらうには、就業形態や属性で差別しない同一労働同一賃金の発想は避けて通れなくなる。つまり、働く人々の属性が多様になれば、異なる属性の人々を公平に評価し処遇することが、企業の発展にとって不可欠になる。そうした意味で、同一労働同一賃金という原理は、処遇の基本として不可欠のコンセプトになっていくであろう。
こうして同一労働同一賃金が浸透していく背後では、賃金体系が変わり、雇用の在り方も変わるであろう。まず、賃金カーブのフラット化が予想される。非正規賃金を引き上げるには、飛躍的な生産性向上がない限り、正社員の賃金原資からねん出するしかない。そのためには、正社員賃金の年功カーブの傾きを緩やかにし、非正規の能力レベルに応じた昇給を可能にする必要性が出てくる。
そうした過程で、雇用の流動化も高まることになるだろう。かつての正社員は、60歳での定年を前提に、長期雇用を前提に働き盛りの賃金は生産性に比べて少な目に払い、中高年時には生産性を上回る賃金を支払うことで、長期的に賃金と生産性のバランスをとってきたとされる。つまり、平均的なケースでいえば、若いうちに転職すれば生産性に応じた賃金が受け取れない仕組みになっていた。しかし、賃金カーブがフラット化し、それぞれの時点における生産性と賃金が近づけば、年齢にかかわらず転職で不利益を被ることはなくなってくる。
しかも、男女共働きが当たり前になれば、家族全体での収入のリスク分散ができるようになり、転職がしやすくなる。終身雇用・年功制の外に位置づけられる60歳以降の就労が当たり前(必要)になれば、実力を認めてくれる企業への転職・再就職が増えるであろうし、それを見越して若いうちから一企業に頼らない実力を身に着けることに本気になる人が増え、結果として、転職が増えていくであろう。
賃金体系・雇用制度が変わり、キャリア形成の在り方も変わる
このように、同一労働同一賃金が本来の文脈で普及していくことで、雇用の流動化が進むことが予想されるが、正確に言えば、同一労働同一賃金の導入が雇用の流動化を進めるというよりも、人口動態の変化に対応するために、賃金体系・雇用制度が同時に変わっていくということである。
こうして賃金体系・雇用制度が変わっていけば、キャリア形成の在り方も大きく変わる。従来の就社型の雇用では通用せず、プロフェッショナルとして自立して、複数の企業を経験したり、場合によってはインディペンデント・コントラクターとして独立して働くということが求められよう。こうした働き手の「キャリア自立」が達成できれば、企業としても戦略的に人材ポートフォリオを組み換えることがやり易くなり、収益性向上につながるであろう。
もっともそれは、雇用契約を職能型から欧米型の職務型に単に切り替えれば済む話ではない。職能型の雇用システムには大きな利点があり、それは維持すべきと考える。具体的には、特定の職種を決めずに複数の仕事を経験することは、特に若い時代において、広い視野を身に着けたり、チームワーク精神を体得するのに有効である。
また、欧米型の職務型システムが機能しているのは、その背景に企業を移ってもキャリア形成を継続していける仕組みが構築されていることも見落とすべきでない。「所属企業が変わってもキャリアを継続していけるような社会的な仕組み」として2つのタイプが整備されているのである*3 。
第1は、企業間移動の円滑化の仕組みである。これは、すでに身に着けたスキルや経験をもとに同じ職業・職種での転職がしやすい環境が整備されていることである。米国の場合、専門職能別の協会組織(専門団体)が様々に存在し、専門家としてのキャリアを形成するにあたって専門団体に所属し、継続的に自己啓発を行っている 。加えて、古くから転職紹介会社が様々なサービスを提供しており、その仲介を背景としたプロフェッショナル労働市場が発達している。欧州では労働者の多くは職業別や産業別の労働組合に属し、職種別労働市場が形成されている。スウェーデンでは、非営利財団による「失業なき労働移動促進」の仕組みも形成されている。
第2は、職種間・就業形態間移動の円滑化の仕組みである。これは、未経験者や他からの参入者が新たなスキルを獲得し、新規にキャリアを始める、あるいはキャリアを転換することをサポートする仕組みといえる。米国では、専門職業を育成する大学院である「プロフェッショナルスクール」を修了することが、高給のホワイトカラー専門職に従事するためのパスポート的な役割を果たす 。また、コミュニティー・カレッジという4年制大学への編入前教育や職業教育を提供する2年制の高等教育機関 があり、「若年層を学校から労働市場へ効率的に橋渡しする役割から、社会人を再訓練して労働市場へ戻すまでの役割を担う、まさに地域の起業や産業の人材育成の中継点(ハブ)*4 」の役割を果たしている。欧州では、ドイツやスウェーデンに職業大学制度が存在する。
つまり、職務型の働き方をわが国で普及させるには、単に雇用契約を職務限定型に切り替えればよいという話ではなく、「所属企業が変わってもキャリアを継続していけるような社会的な仕組み」を整備することが重要になる。
キャリア自立のための環境準備を進めよ
そうした意味では、徐々にそういった動きも出てきている。企業間移動の円滑化の仕組みとしては、リクルート社がOB・OGネットワークを形成しているという例があるし、人事のプロフェッショナルの世界では横のつながりが形成され、中途採用で活躍する人材が徐々に登場してきている。業界を挙げた仕組みでは、地銀業界の取り組みが興味深い。全国地方銀行協会全 64行の地銀が連携し、2015年4月に「地銀人材バンク」を創設した。その仕組みは、ある地銀で退職者が出たとき、その退職者が属する銀行から転居先の銀行に受け入れ可能かを打診し、可能であれば紹介元銀行が紹介シートや履歴書を紹介先銀行に送付して、採用の可否が決定される、というものである。基本的には女性行員を想定しているが、男性でも利用でき、今後は親の介護のために転居を余儀なくされるケースも展望しているという*5 。
職種間・就業形態間移動の円滑化の仕組みとしては、政府は2019年度より、実践的な職業教育を行う新たな高等教育機関として「専門職大学」「専門職短期大学」を創設する。その教育内容は、その専門性が求められる職業に就いている者、当該職業に関連する事業を行う者その他の関係者の協力を得て、教育課程を編成、実施することになっており、産業界等と連携した教育を実施することが義務付けられる。教員については、実務家教員を教員組織の中に積極的に位置づけ、必要専任教員数のおおむね4割以上を実務家教員とし、その半数以上は研究能力を併せ有する実務家教員とする予定となっている。
これは、欧米での高等職業教育制度を参考にしているが、その成否は企業が積極的に関与するかどうかにかかっている。具体的には2つのことが望まれる。
第1は、プロフェッショナル人材と大学教員の相互転換・兼務、人材交流を促進することである。プロフェッショナル人材が教えることで、高等職業教育内容の実践度を向上させることが期待できる。一方、プロフェッショナル人材が大学で実証研究や知識の体系化に取り組み、それをもとに産業界で実践してみる、あるいは、大学教員が民間企業(主に研究所)で一時期働く、といった人材交流が積極的に行われるようになれば、「プロフェッション(知識・スキルや行動規範が理論化・体系化された職業)」が高度化していくであろう。つまり、「プロフェッションの高度化」と「職業教育の実効性向上」の好循環を形成することを目指すべきである。
第2に、職業人生の早い段階からの、節目節目でのキャリアの棚卸の実施である。私見では、職能型の雇用システムの利点を維持するために職業人生前半は就社型で、途中からプロ型に転換するのが望ましいと考える。しかし、一定の年齢を過ぎて急に転換できるものではない。キャリアコンサルタントの支援のもとで、職業人生の前半期からの人事部面談を行うほか、定時退社を一般化させることで自己啓発を促す等、中高年期に向けてキャリア自立が可能になる総合的な支援体制を構築すべきであろう。
従業員のキャリア自立を支援することは、優秀な人材の社外流出につながるということで、企業の人事部には慎重論もあるだろう。しかし、すでにみたように、雇用流動化は必然の流れであり、放っておいても優秀な人材の自立志向は高まる。むしろ人材獲得のためにこそ企業は取り組むことが求められ、多くの企業がキャリア自立支援で競うことで、より多くのプロフェッショナル人材が育ち、日本企業全体の発展につながっていくであろう。

参考文献
*1 労働政策研究・研修機構(2011)『雇用形態による均等処遇についての研究会・報告書』
*2 JILPT「平成27年 労働力需給の推計」における、経済再生・労働参加進展シナリオの年齢階層別数字により算定。
*3 詳しくは拙著『失業なき雇用流動化』慶應義塾大学出版会、2015年
*4 黒澤昌子(1999)「高等教育市場の変遷―米国における例をもとに」八代尚宏編『市場重視の教育改革』日本経済新聞社、第6章
*5 日本の人事部ホームページ となりの人事部インタビュー 第68回輝く女性の活躍を加速する地銀頭取の会による。
この記事を書いた人
山田久 氏 株式会社日本総合研究所 理事/主席研究員、博士(経済学)
1987年京都大学を卒業後、同年住友銀行(現三井住友銀行)入行。91年(社)日本経済研究センター出向、93年(株)日本総合研究所出向、調査部研究員、2003年経済研究センター所長、05年マクロ経済研究センター所長、07年ビジネス戦略研究センター所長、11年(株)日本総合研究所調査部長、17年(株)日本総合研究所理事。また、2013年より法政大学大学院イノベーションマネジメント研究科客員教授、16年同兼任講師。近著に「同一労働同一賃金の衝撃」(日本経済新聞出版社)。