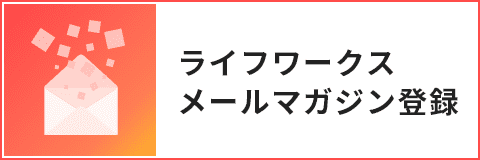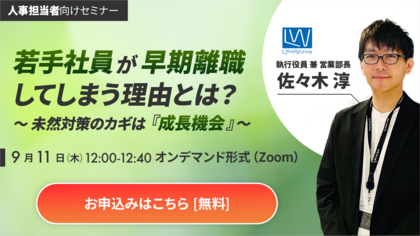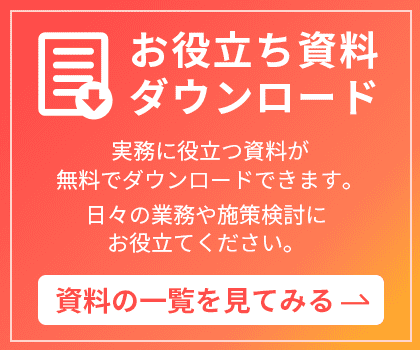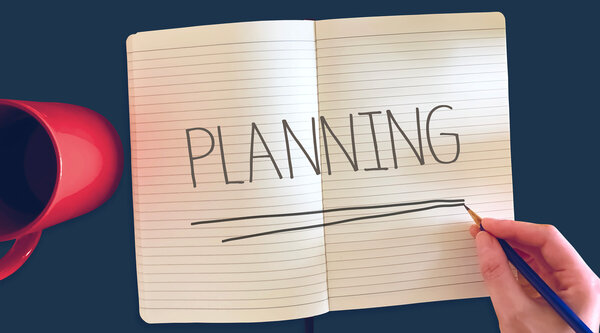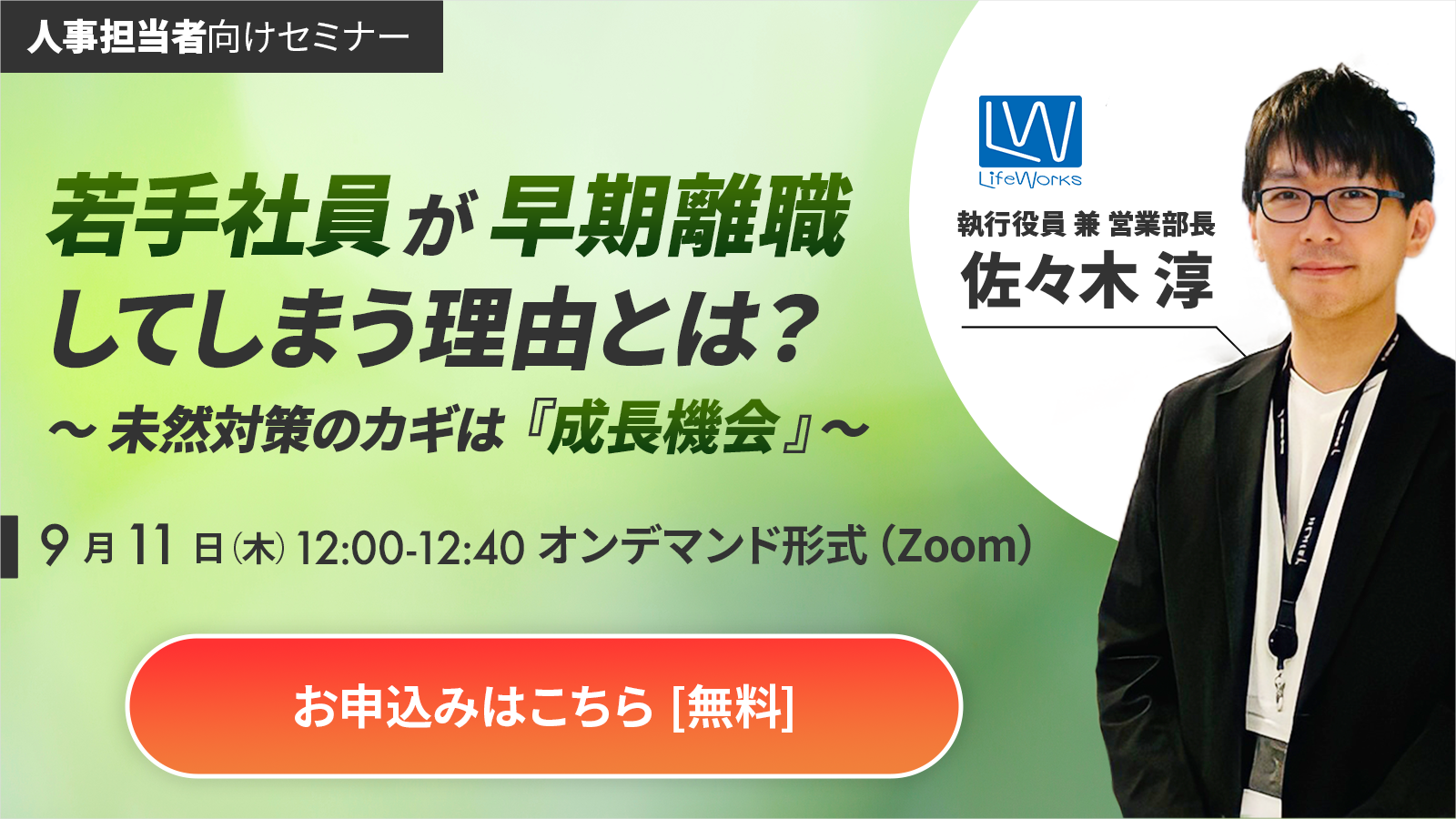キャリア自律とは?定義や必要性、企業が支援するメリットを解説
キャリア自律は、テクノロジーの発展によるビジネス環境の変化や、企業の組織や制度の変革に伴い、今日では注目の高い概念のひとつとなりました。また、ここ数年テレワークを導入する企業が増えたことで、企業と働く個人の関係性が変化しており、そうした観点でもキャリア自律はより重要な概念になってきています。
今回は、キャリア自律の定義、キャリア自律が注目される理由、企業がキャリア自律を推進するにあたっての課題、キャリア自律の方法、といったことを皆さんと考えてみたいと思います。

1.キャリア自律とは
キャリア自律(Career Self-reliance)とは、みずから主体的に価値観を理解し、仕事の意味を見出し、キャリア開発の目標と計画を描き、現在や将来の社会のニーズや変化を捉え、主体的に周囲の資源などを活用しながら学び続け、不断にキャリア開発することです。
1990年代にCAC(Career Action Center、米カリフォルニア)が新しいコンセプトとしてキャリア自律の定義とモデルを提唱したことをきっかけに、働く人のキャリアを捉え、支援するための概念として用いられるようになりました。また、この概念はそれまで主に使われていたキャリア開発(Career Development)に比べ、自己理解による気づきや自己変容に焦点を当てていることが特徴といわれています(例えば、花田ら2003)。
こういった定義や特徴を踏まえつつ、ドナルド・スーパーのキャリア開発の理論を発展させたと言われるマーク・サビカスの「キャリア・アダプタビリティ」の関心(Concern)、統制(Control)、好奇心(Curiosity)、自信(Confidence)という4つの要素も併せて考えると、キャリア自律には、自らを律しつつも、自身のキャリアに関心を持ったり、キャリア開発を進めることに自信を持ったり、起こる周囲の変化に好奇心を持ったり、というような心理的側面も重要な要素と考えられます。
なお、自律と似た言葉に自立があります。外部の力に指示されずとも、自身をコントロールして行動することを意味するのが自律です。一方で自立とは、外部の助けを借りずに、自身の力だけで行動することを指す言葉です。
これらの言葉の違いを社員と結びつけると、自律した社員とは、自分の意思を持ちつつ自らをコントロールでき、さらに他者のニーズも把握した上で自己実現を図れる社員のことです。一方で、自立した社員とは自分の意見や主張を持ち、自ら行動できる社員であるといえます。一見これらの言葉は似ているように思えますが、自律には企業などの周囲に人がいる環境のなかで、周囲の期待を捉え自らをコントロールして行動できるという、外部環境に対する視点も含まれています。
【参考資料】特別講演「普通の人がイキイキする人事・キャリア支援のありかた」講演録
慶應義塾大学名誉教授 花田光世先生に登壇いただいたセミナーの講演録です。ダイバーシティ時代における普通とは、キャリア支援における個人の能力開発の重要性、などの話題のほかに、これからの人事のあり方やキャリアコンサルタントの役割などについてもお話しいただきました。講演録はこちらからダウンロードしてください。
2.キャリア自律が注目される背景
日本においてキャリア自律に注目が集まっている理由としては、どのようなことが挙げられるのでしょうか。ここでは、代表的な3つの背景についてそれぞれご説明します。
1)労働人口の減少に伴い、生産性の向上が必要になったこと
1998年に労働人口がピークを迎えた日本は、人口オーナスともいえる状況にあります。そのため、成長し続けるには、生産性を上げることが課題といわれるようになりました(総務省「労働力調査」を参照)。
日本生産性本部の調査研究(2019)によると、1970年以降、先進7ヵ国の中で日本の労働生産性は最下位のままになっています。このようなことも、生産性に注目が集まる理由の一つといえます。
生産性向上に寄与すると考えられる一つの方法が、キャリア自律です。なぜなら、働く一人ひとりが自ら考え、主体的に行動することが、仕事で高いパフォーマンスを発揮することにつながると期待されるからです。
2)年齢や勤務年数に応じた活躍から、あらゆる世代の活躍が必要になったこと
働くことに関するテーマが、2015年から2020年にかけて「女性活躍推進」から、誰もが活躍する社会を推進する「ダイバーシティ推進」に変わりました。この「誰もが」には女性、高年齢人材、障害者、就職氷河期世代を含め、あらゆる年代の人材が含まれています。
誰もが活躍を期待される社会へ向けて、例えば、日本型雇用の特徴の一つといわれる、年功序列にメスが入れられるようになりました。新卒で特殊スキルを持つ人材に対して高い初任給を設定する企業や、ジョブ型雇用を導入する企業が増えてきたことは、勤続年数による処遇を仕事内容や役割に応じた処遇へと見直すようになったことのあらわれだといえます。
このような流れの中では、一人ひとりに年齢に応じたキャリアのレールが用意されません。そのため、個人はそれぞれに自身の能力を最も発揮できる道を探りつつ、主体的にキャリアを選択することが求められるようになります。
3)個人の価値観や働き方が多様化し、企業と個人の関係性が変わりつつあること
「VUCA時代」(Volatility:変動、Uncertainty:不確実、Complexity:複雑、Ambiguity:不透明)という言葉に代表されるように、世の中の変化が激しく、将来の予測がつきにくくなり、企業は過去の成功体験にもとづくだけでは社員のキャリア開発の推進が難しくなりました。
そして、働く人たちの価値観は「仕事を通した成長」だけではなく、「家族との時間を大切にする」、「余暇を楽しむ」、「ボランティアで人の役に立つ」というように、人生の中の様々な役割を通して自己実現をしたいといったものに多様化してきています。
また、副業や兼業といった働き方の選択肢が増えた現在では、個人は所属する組織、雇用形態だけではなく、誰とどのように働きたいか、それはなぜかを考えながら、一人ひとりのキャリアをみずからが選び、決断し、行動することができるようになりつつあります。
このような状況において、企業は個人ができること、成し遂げたいことについてよりアンテナを張り、個人とどのようにつきあい、対等な関係を築くことで互いに成長を遂げることが重要なテーマになっているといえます。
例えば、法政大学の諏訪名誉教授による「キャリア権」(「働く人が自分の意欲と能力に応じて希望する仕事を選択し、職業生活を通じて幸福を追求する権利」)に関する議論も、このような世相を捉えたものの一つだといえます。
3.企業における社員のキャリア自律支援の3つの課題
先の3つの背景を企業の視点としてまとめると、多様なキャリア観を持つ社員一人ひとりの生産性を上げ、個人と企業が互いに成長する関係性を築くことが今日の企業の課題になってきているといえます。他方で、働く個人は自らのキャリアに関心と責任を持ち、主体的にキャリアを開発し続けることが課題といえます。
ですが、会社員としてのキャリアを経験してきた人の中には、自身のキャリアを企業の人事に委ねてきた人もある程度存在します。年代に関わらず、社会人になるまでキャリア教育を受けておらず、企業に所属するようになってからはジョブローテーションや異動に任せながらキャリア形成を進めてきた人などは、唐突に「これからは自身でキャリアを形成せよ」と言われても、戸惑いや不安を抱くかもしれません。ましてや、それを行動につなげていくにあたってはハードルがいくつか存在します。
そういった人の意識を、「キャリアは自ら切り開くものだ」というように変え、自らキャリア形成できるように支援していくことも企業の課題ということができます。
企業が社員のキャリア自律を支援することの難しさには、個人の意識の変革だけではなく、いくつかの課題があると考えられます。
1)キャリア自律を促すことへの、企業側の懸念
人材育成の施策の一環として、選抜した社員を国内外のビジネススクールに派遣する、あるいは副業・兼業、ボランティアなどを通じて社員に多様な経験をする機会を設ける、といった施策を導入する企業もあれば、ためらう企業もあるようです。
ためらう理由の一つとして、社員が社外での交流をきっかけに転職してしまうおそれを挙げる企業は少なくありません。
ですが、こういった社外での交流は必ずしも離職につながるものではないことは、いくつかの調査で明らかになっています。
リクルートキャリア調査(2020)で「副業や兼業を推進または容認している企業」の回答の一部
「離職防止」を副業や兼業の導入背景とした割合 27.6%
「離職防止やエンゲージメント向上に効果があった」と回答した割合 35.6%
「副業や兼業から本業への還元があった」と回答した割合 34.0%
リクルートキャリア(2020)「「兼業・副業に対する企業の意識調査(2019)」より
2019年調査では、副業・兼業に前向きな企業の割合は全体の30.9%(副業・兼業を推進4.4%と容認26.5%の合計)となっているため、割合こそ多いとはいえませんが、副業や兼業について「離職防止」の効果が期待以上に見込まれる様子をうかがうことができます。また、同調査からは副業や兼業が人材の更なる活躍や、優秀な人材の社外からの獲得につながることが期待されていることもわかります。
いずれにしても、もしキャリア自律について少しでも懸念を抱いているのであれば、このような調査の結果などを踏まえて、キャリア自律は転職や早期退職といった人材流出にのみつながるものではないということも理解し、施策の設計や導入を考える必要があるといえます。
【関連情報】「ロート製薬の兼業解禁の事例」
政府が副業や兼業の議論を始めるよりも先に、兼業制度を開始したロート製薬で、施策の検討から実行までを担った方への取材記事です。当時は、副業・兼業に何を期待し、どのような工夫をしたのかを伺いました。詳細にご関心のある方は、こちらをご覧ください。
2)キャリア自律支援への上司の理解不足
キャリア研修などの施策により、本人のキャリア自律への意識が高まったものの、日常の業務に戻ったら上司の理解が得られず、思うように行動に移せないという課題があります。
望ましい姿は、上司が部下のキャリアに関心を持ち、キャリア自律に向けた行動を支援することですが、上司の役割自体が部下の業績向上の支援になっていることもよくあります。そのため、定期面談は上司から部下への短期的な目標達成に対するフィードバックや実績評価に終始しがちになります。場合により、そもそも上司本人がキャリア自律やその必要性について理解していないこともあります。
こうした状況を解決するために必要なのは、まず上司自らがキャリアを描ける状況をつくること。そして、長期的なキャリアを考えることの重要性を理解した上で、部下のキャリア自律を支援するための意識を持ったりノウハウを習得したりすることです。
3)すべての社員への期待役割を明確化し浸透させることの困難さ
「30代社員には企業が期待する役割を正しく捉え、主体的に対応しながら、専門性を発揮する人材へと成長してほしい」。「40代社員は専門性を発揮し、中心となって事業を推進してほしい」。
組織がこのように願っていても、社員が組織からの期待を正しく捉えて主体的に動くことは、上司と部下の関係だけで解決できるとは限りません。時に組織的な課題がボトルネックになっていることもあります。
こういったケースでは、一人ひとりがキャリア自律意識を持ち続けながら、行動するようになるためには、組織全体としてその実現を後押しするような環境になっていることが必要だといえます。
そのためには、自社にとってのキャリア自律を定義し、各個人に期待する役割を明確にして正しく伝え、フィードバックすることが必要です。さらには、キャリア自律が浸透するためのプロセスを仕組みとして構築しておくことが、企業にとって重要な課題になります。
4.社員のキャリア自律支援による企業側のメリットとは?
社員のキャリア自律支援を行うことで、企業はどのようなメリットが得られるのでしょうか。
ここでは代表的な3つのメリットについて、それぞれ説明します。
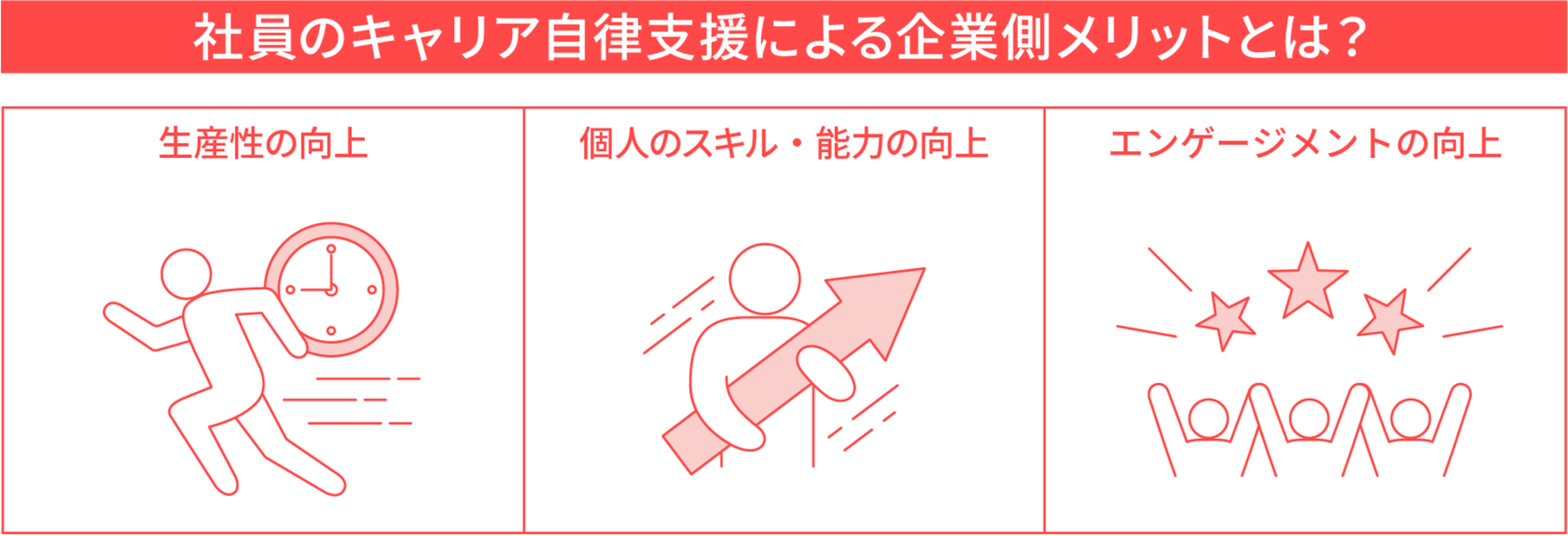
1)生産性の向上
生産性の向上は、キャリア自律によるメリットのひとつです。
キャリア自律支援を通して自律的な社員が増えれば、従業員が主体的に学習・経験を積んで成長を目指すようになります。それによって、社員一人ひとりがスキルアップやキャリアアップへ向けて何をすべきかを考えるようになるため、生産性の向上も期待できるでしょう。
2)個人のスキル・能力の向上
キャリア自律支援は、社員一人ひとりのスキルや能力を向上させることにもつながります。業務上必要なスキルを一律に取得させる人材育成とは異なり、キャリアを自律的に考えることができるようになると、社員自らが目的を設定して行動するようになると見込めるためです。
社員が個人で目標を設定するにあたって重要となるのは、自身の成長イメージや目指すキャリアを描けていることです。企業がキャリア自律を支援することで成長イメージやキャリアを自発的に描けるようになり、その結果、個人のスキル・能力の向上にもつながるでしょう。
3)エンゲージメントの向上
キャリア自律支援という形でキャリア構築を支援・応援してくれる企業に対して魅力を感じる社員も一定数いるでしょう。従業員のキャリア構築に理解がある企業だと社員が理解し、その組織で働く意義が高まることでエンゲージメントが向上し、リテンションにつながる可能性があります。
また、社員のキャリアビジョンを企業が把握・理解できる環境があり、企業の方向性と重なってチャレンジする機会を得られるのであれば、社員と企業の双方にメリットのある関係性を構築できます。
5.社員のキャリア自律を支援する方法
キャリア自律の促進は、社員がモチベーション高く、働きがいを感じながら働くようになったり、自ら新しいことに挑戦したりといったことにつながると期待されます。また、キャリア自律によって離職を防いだり、優秀な人材を社内外から獲得できたりするなどのメリットも考えられます。さらに、キャリア自律した社員が増えることで、組織全体は活力にあふれ、高い成果を生み出すことが期待されます。
ですが、即効性のあるキャリア自律支援の施策はほとんどないといっても過言ではありません。つまり、キャリア自律支援の施策は、短期ではなく、中長期の人材への投資と考えることが重要です。
下記に、キャリア自律を支援する方法をご紹介します。
<キャリア自律を支援する主な方法>
- キャリア研修
- キャリアカウンセリング/コーチング/キャリア面談/メンター制度
- メンター制度
- 副業・兼業などの越境学習
- 学習機会の提供や費用支援
1)キャリア研修
自身の価値観や強みを把握するのに有効な方法としては、自己理解のためのアセスメントやそれを活用したキャリア研修などが例として挙げられます。
アセスメントの結果は客観的な視点から自身の強みや価値観の再認、あるいは発見につながりやすく、個人の価値観の整理に役立ちます。キャリア研修は、講師による介入もさることながら、参加者同士のグループダイナミクスによる気づきを多く得られる場として有効です。
アセスメントとキャリア研修を組み合わせることで、概ね1年~5年ぐらい先のキャリア形成のイメージを明確にすることが可能ですが、参加者自らが決めたキャリアに関心を持ち、行動に移し、実行し続けるようになるためには、30代、40代、50代と、世代ごとにキャリア研修を実施するなど、継続的な支援が必要です。
2)キャリアカウンセリング/コーチング/キャリア面談/メンター制度
行動を促進したい場合、キャリア研修だけでは不十分な場合もあります。というのも、スポット的に行われた体験による成果は、実務に戻った後で忙しさや自分のイメージとは違ったという経験によって、薄れていく可能性も否めないからです。
そのような場合は、定期的、あるいは不定期であっても状況を確認できる場を設けることが重要です。例えば、キャリアカウンセリングを利用して、自身がイメージしていることがなぜうまくいかないのか、どうしたらうまく進むのかを確認できるコーチングを受けることで、次に取るべき行動を明確にしつつ一歩一歩進んでいけるようになるでしょう。
そのほかに、上司とのキャリア面談、メンター制度といったものも、このような確認の機会として活用できます。特にこれらの施策は組織内で活躍するイメージを具体化し、行動につなげるために用いることができます。
【参考資料】上司と部下のキャリア面談を成功させるポイント(面談サンプルシート付)
このコラムでお知らせしているキャリア面談を上司が成功させるためのポイントを簡単にまとめた資料です。面談で使うシートのサンプルもございますので、併せてご活用ください。資料はこちらからダウンロードしてください。
3)副業・兼業などの越境学習
将来のニーズを知ったり、そこに向かって自らのキャリアを不断に形成したりするためには、自身の能力にどれだけの市場価値があって通用するのか、どれくらいのコミュニケーションスキルがあるのか、他者との協働を図ることができるのかといった、いわゆるエンプロイアビリティスキル(雇用される能力)を知る必要があります。
エンプロイアビリティスキルを自覚するには、社内では通用するスキルが通用しない経験ができる副業や兼業、越境的学習といった、いわゆる他流試合の場が有効です。そういった場を活用することで、社員は自らが発揮できる現在の価値や能力を確認できるだけではなく、先を見据えて不足部分を補足するきっかけを得ることにも期待できます。
あるいは、社外の人との交流で得られた新たなネットワークが、普段とは違った視点を養い、仕事上の工夫につながることや、仕事で不足するリソースの獲得に至ることもあります。
4)学習機会の提供や支援
社会人が継続的に学習したり、学びなおし(アンラーニング)をしたりする場所の代表的なものとしては、社会人大学院やビジネススクールなどが挙げられます。ですが、こういった場に身を置くことで、時間的にも経済的にも負荷がかかることは否めません。そのため、学びなおしの場については、目的や経済的環境などを加味して、自身のキャリア形成につなげるために選択可能なものを候補に挙げる必要があります。
学習・学びなおしの場所としては下記が挙げられます。
<学習・学びなおしの主な場所>
- 社内スクールやE-ラーニング
- 社内の公式・非公式のワーキンググループ
- 特定のビジネステーマに関心のあるメンバーが集まるコミュニティ
- NPO法人などの団体が主催する勉強会
このように、私たちの身の回りには様々な興味・関心のあることについて学ぶ場が多数存在しますので、足を運ぶ機会さえあれば誰しも学びなおしが可能です。そして、学びなおしをうまく行うためには、本人がこれまでのやり方に固執せず、変化を受け入れる柔軟な姿勢を持つことが欠かせません。
5)状況の明確化
キャリア自律を促す方法は実に多様です。まずは社内にどのような課題があるのかを明確化する方法もあります。その代表的なものがリサーチです。
リサーチにも実に様々なアプローチ方法が存在していますが、代表的なものは下記のとおりです。
<リサーチするための主な方法>
- 従業員エンゲージメントを測定するもの
- 従業員満足度を測定するもの
- キャリア意識やキャリア自律の度合いを測定するもの
それぞれのリサーチで用いられる尺度については、学術的に検証されながらビジネスの現場にも応用されているものが多くありますので、できる限り信頼のおける尺度を用いたものの活用が好ましいでしょう。
そのほかに状況を明確化する方法としては、例えばタレントマネジメントのシステムなどを用いて社員情報をデータベース化することなども有効です。
キャリア自律を促すために、自己申告制度、社内公募制度、ジョブローテーションといった様々な制度を用いることもあります。こういった制度が実行力のあるものにするためにも、社員一人ひとりのキャリア自律促進をどのように進めるかということを並行して検討し、全体的にどのようなキャリア開発の仕組みを作り上げていくのかという設計図を作ることが、何よりも大切だといえるでしょう。
【参考資料】キャリア開発事例集
キャリア開発の事例集です。キャリア研修や、キャリア開発のための仕組みづくりや体制の構築といったものをご紹介しています。定年延長への対応やシニアの職域開発といったことにご関心がある方も、ぜひ参考にしてください(上記の【事例2】の要約版も収録)。事例集はこちらからダウンロードしてください。
【参考資料】キャリア自律調査
この調査では、社員のキャリア自律の現状とそれに影響を与える要因を詳細に分析します。具体的には、キャリア自律の状況、仕事の充実感、キャリア展望、職場での居場所感、組織へのコミットメントといった項目を調査し、これらを数値化して自社の課題を明らかにします。これにより、人事や教育担当者はキャリア開発支援のための研修や体制構築、既存の取り組みの改善策を検討しやすくなります。
調査の詳細はこちらをご覧ください。
参考文献・資料:
Byster, D. (1998). A Critique of Career Self-Reliance. Career Planning and Adult Development Journal, 14(2), 17-28.
Collard, B. A., Epperheimer, J. W., & Saign, D. (1996). Career resilience in a changing workplace. ERIC Clearinghouse on Adult, Career, and Vocational Education, Center on Education and Training for Employment, College of Education, the Ohio State University.
花田光世, & 宮地夕紀子. (2003). キャリア自律を考える: 日本におけるキャリア自律の展開. CRL レポート.
リクルートキャリア(2020)「「兼業・副業に対する企業の意識調査(2019)」
Waterman Jr, R. H. (1994). Toward a career-resilient workforce. Harvard Business Review, 72(4), 87-95.
6.【補足】キャリア自律の定義について
CACによって1995年に示されたキャリア自律の定義は、「めまぐるしく変化する環境の中で、自らのキャリア構築と継続的な学習に積極的に取り組む、生涯にわたるコミットメント」というものでした。
また、このCACによる定義は、次の6つの特徴を持つものとされています。
1)自己理解(Self-Aware)
自分が誰で、どこでどのように働くのが最良かを知る。自らが付加する価値を理解し、明確にすることができる。
2)価値主導(Value-Driven)
自らの仕事を方向づけ、意味づける価値にもとづいている。
3)継続的学習(Dedicated to Continuous Learning)
定期的にスキルのベンチマークを行い、個人的および専門的な開発計画を作成して、スキルを最新の状態に保つ。
4)未来志向(Future-Focused)
先を見据えて、顧客のニーズとビジネスの傾向を見積もる。自身の仕事および開発計画におけるそれらの傾向の影響について考慮する。
5)ネットワーキング(Connected)
アイディアを学んだり、共有したりするための連絡先のネットワークを維持する。互いの目標に向かい、他の人と協働する。
6)柔軟性(Flexible)
変化を予測し、すぐに適応する準備ができている。
以上の定義などを踏まえると、キャリア自律とは、自ら主体的に価値観を理解し、仕事の意味を見出し、キャリア開発の目標と計画を描き、現在や将来の社会のニーズや変化を捉え、主体的に周囲の資源などを活用しながら学び続け、不断にキャリア開発することだと理解できます。
株式会社ライフワークスでは、従業員が自律の意識と行動を高めて自ら成長できる企業へと変革していく「キャリア開発の仕組み・体制構築支援サービス」をご提供しています。セルフ・キャリアドック導入や、社員のキャリア自律に課題を持つ方は、是非ライフワークスのキャリア開発の仕組み・体制構築支援サービスをご覧ください。
7.よくある質問
1)キャリア自律とはどういう意味ですか?
キャリア自律とは、自ら価値観を理解して仕事の意味を見出し、キャリア開発の目標と計画を描き、現在や将来の社会のニーズや変化を捉え、主体的に周囲の資源などを活用しながら学びつつキャリア開発することを意味します。
1990年代までに主に使われていた「キャリア開発」と比べて、自己理解による気づきや自己変容に焦点を当てていることが特徴とされています。
2)キャリア自律の重要性とは?
企業がキャリア自律支援を行うことで、従業員が主体的に学習・経験を積んで成長を目指すようになり、生産性の向上につながります。また、キャリア自律が促進され、社員自らが目的を設定して行動するようになることで、個人のスキル・能力の向上も期待できます。
さらに、社員は自分のキャリア構築を支援・応援してくれる企業に魅力を感じるため、キャリア自律支援をすることで、エンゲージメントの向上にも効果を発揮するでしょう。
3)キャリア自律が求められる背景は?
キャリア自律が求められる背景として、労働人口の減少に伴い、生産性の向上が必要となったことが挙げられます。また、ダイバーシティの推進によって、従来の「年齢や勤務年数に応じた活躍」から「あらゆる世代の活躍」が重視されるようになったことや、個人の価値観や働き方が多様化し、企業と個人の関係性が変化しつつあることもキャリア自律が必要とされる理由といえるでしょう。
この記事の編集担当

黄瀬 真理
大学卒業後、システム開発に関わった後、人材業界で転職支援、企業向けキャリア開発支援などに幅広く関わる。複業、ワーケーションなど、時間や場所に捉われない働き方を自らも実践中。
国家資格キャリアコンサルタント/ プロティアン・キャリア協会広報アンバサダー / 人的資本経営リーダー認証者/ management3.0受講認定
talentbook:https://www.talent-book.jp/lifeworks/stories/49055
Twitter:https://twitter.com/RussiaRikugame
Linkedin:https://www.linkedin.com/in/marikinose/