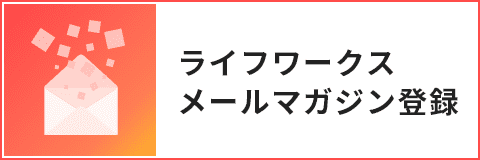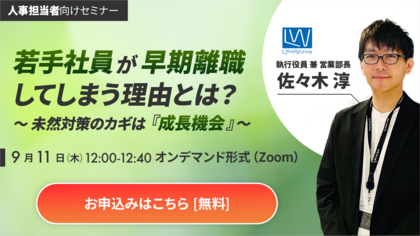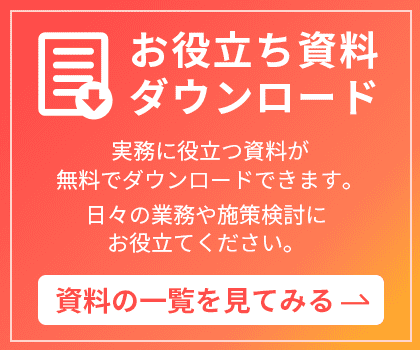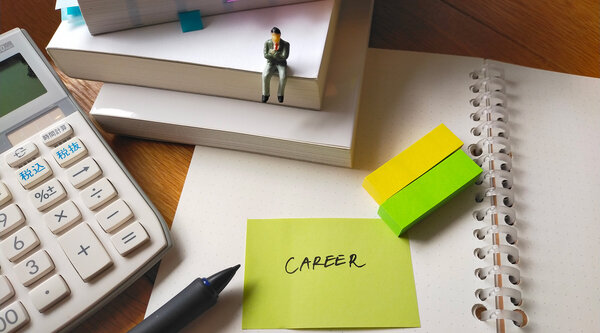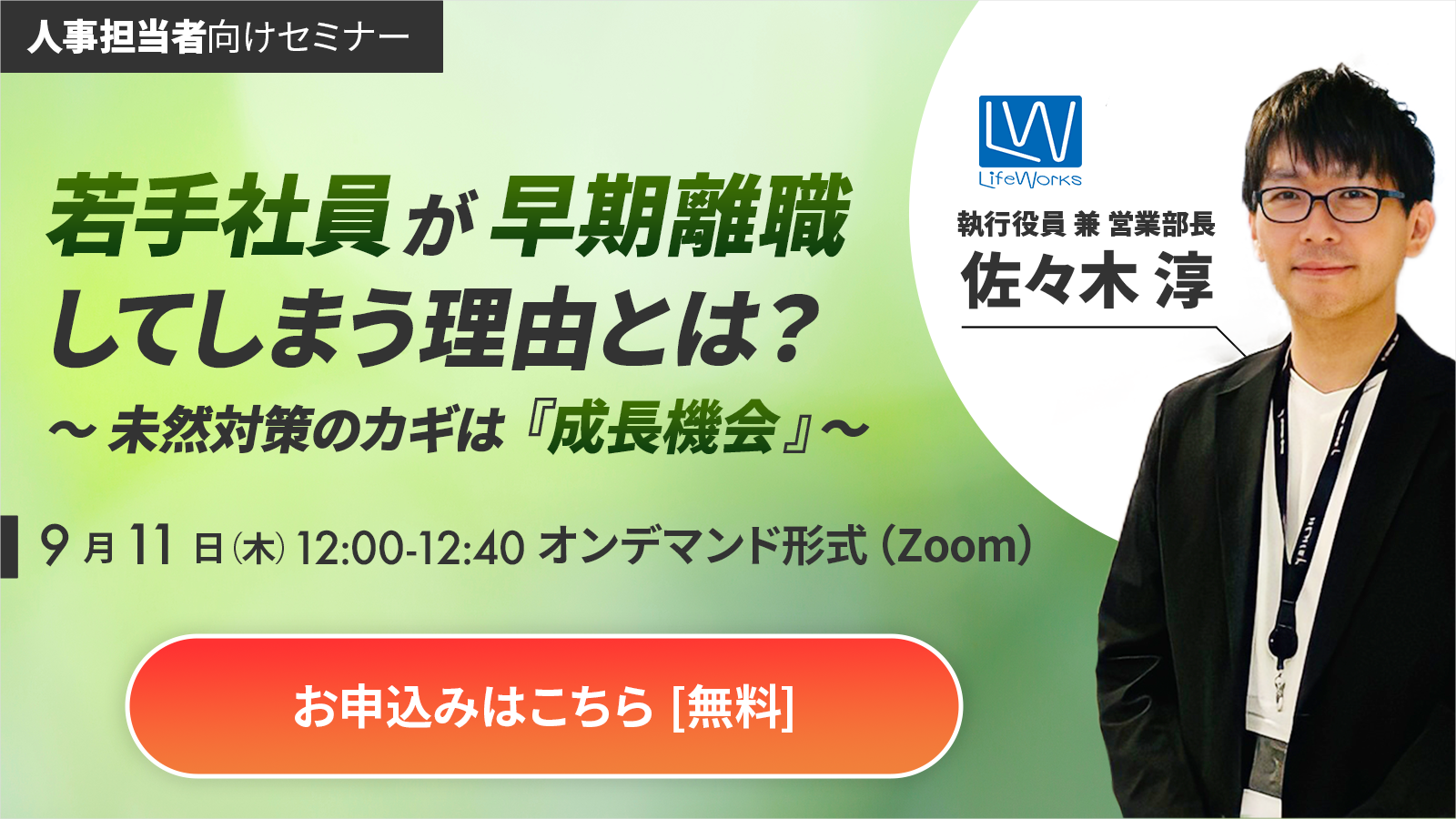自律型人材とは?育成方法とメリット・デメリットを解説
急速なグローバル化、デジタル化など、企業を取り巻く環境は激しく変動し続けています。こうした状況下で、個々人が指示待ちの働き方をしていると、組織全体として変化のスピードに追いつけず、企業の競争力が低下する可能性があります。昨今、組織の持続的な成長を支える重要な存在として注目を集めているのが「自律型人材」です。
しかし、自律型人材の育成に力を入れようと思っても、社内にどれだけの自律型人材がいるのかといった現状把握に困っていたり、具体的にどのような支援を行えばよいか悩んでいたりする企業も多いのではないでしょうか。
この記事では、自律型人材の特徴や必要性、自律型人材を育成する方法などを解説します。

1.自律型人材とは、指示を待つのではなく主体的に行動計画を立てて実行できる人材
自律型人材とは、自ら主体的に行動計画を立てて実行し、変化に対応しながら新たな価値や役割を創造していく人材のことです。指示を待つのではなく、自らの意思で考え柔軟に行動できる自律型人材は、多くの企業で求められています。
ただ、自律的に動くといっても、個々が好き勝手に行動するという意味ではありません。企業のビジョンや経営目標を理解すること、自らも社会のニーズを考えること、さらに新しい知識を学びながら積極的に活かすことなどができる人材が、自律型人材といえるでしょう。
1)自立と自律
自律型人材を考える上で、混同されやすいのが「自立」と「自律」です。
自立とは、外部の助けを借りずに、自身の力だけで物事を行うことを指す言葉です。それに対して自律は、外部からの指示に頼らず、自分で自分をコントロールしながら行動することを意味します。自律は、周囲の人や環境のなかで自らをコントロールしていくという外部環境への視点を含む点において、自立とは異なります。
2)自律型人材とキャリア自律
自律型人材と混同されやすい言葉として、「キャリア自律」があります。キャリア自律とは、個人が主体的に自分のキャリアを考え、自律的にキャリア開発を行っていくことです。具体的には、自らが社会のニーズや変化を捉えて学び続け、継続的にキャリアを開発することを意味します。
一方で、自律型人材とは、組織内での具体的な業務やプロジェクトに対して自己主導的に取り組む能力を持つ人材を指し、目標達成に直接貢献することに焦点を当てています。
自律型人材とキャリア自律はそれぞれ違う意味を持つ言葉です。しかし、自律型人材を育成するにあたっては、キャリア自律が前提となる部分があります。
キャリア自律については、下記の記事をご覧ください。
キャリア自律とは?企業が支援する際の注意点やポイントを解説
2.自律型人材の必要性
ビジネスを取り巻く環境が急速に変化している現代において、企業が競争優位性を保つためには、変化に柔軟に対応しながら目標達成に向けて業務を進めていく必要があります。このような時代に必要になるのが、自律型人材です。変動性が高く不確実な社会では、従来の成功体験や経験値では対応しきれないことも起こりえます。指示を待つのではなく、自ら考えて新しいことにチャレンジをし続けることが求められるのです。
このような変化に組織全体として迅速に対応するには、主体的に行動できる自律型人材の存在がカギになります。
社内に自律型人材の割合が増えれば、現場社員が変化を感じ取ることができ、柔軟な対応力が組織能力に加わるでしょう。結果として企業活動のスピード感が増し、それが生産性の向上にもつながります。
3.自律型人材の特徴
自律型人材には、共通するいくつかの特徴があります。代表的な3つの特徴を下記にご紹介しましょう。
■自律型人材の特徴

1)自ら行動する
自律型人材の大きな特徴は、上司からの指示を待つのではなく、自ら行動できることです。自律型人材は、自らに課せられた役割や期待を理解し、自分で判断して行動に移すことができます。
2)強い責任感がある
責任感の強さも、自律型人材の特徴のひとつです。自ら目標を設定して主体的に行動する自律型人材は、自分が立てた目標や行動計画に対して、最後まで責任を持って取り組むことができるでしょう。たとえミスやトラブルがあっても、途中で投げ出すことなく、状況を把握しながら対応・改善していく力があるといえます。
3)独自性を発揮できる
自律型人材には、周りに流されずに、独自性のあるアイディアを仕事に反映できるという特徴もあります。自律型人材は、組織の戦略を考慮しながら、自分の価値観にもとづき行動できます。他人の意見に振り回されたり、場の雰囲気に流されたりするようなことはありません。確固たる「自分」を持って判断できるため、オリジナリティを発揮できます。
4.自律型人材が活躍しやすい組織
自律型人材がより活躍しやすいといわれる組織形態の一例として、「ホラクラシー組織」と「ティール組織」があります。それぞれどのような組織なのかを見ていきましょう。
1)ホラクラシー組織
ホラクラシー組織とは、社内に役職や階級のないフラットな組織形態のことです。意思決定権が部署やチーム、個人など、組織内で分散されているのが特徴です。社員それぞれに意思決定権が与えられるため、主体的に行動できる自律型人材が能力を発揮しやすい環境といえます。
2)ティール組織
ティール組織とは、組織の目的実現のために、メンバー全員が個別に自己決定を行う組織のことです。従来のピラミッド型の指示命令系統が存在せず、組織内の関係性がフラットであることが特徴です。個人が意思決定する組織なので、一人ひとりが自律型人材であることが前提となります。
5.自律型人材を育成する方法
自律型人材を育成したいと考えていても、「具体的にどうすればいいのだろう」と悩む企業は少なくありません。ここからは、自律型人材を育成するための具体的な方法について解説していきます。
1)自社にとっての自律型人材を定義する
育成にあたってまず必要なのは、自律型人材を定義し自社で同じ認識を持てるようにすることです。一口に自律型人材といっても、人によって認識やイメージは異なる場合があります。そのため、「自律型人材とはどのような人材なのか」を明確化しましょう。このとき、なぜ自律型人材が必要なのか、どのような期待があるかを具体的に言語化しておくことがポイントです。
また、社内にすでに自律型人材がいる場合は、その人物の行動を観察し、持ち合わせているスキルやマインドを分析することで、自律型人材像を定義するという方法もあります。
2)環境を整備する
自律型人材の育成を促進するには、主体的な発言や行動が奨励される環境を整えるとよいでしょう。失敗が許されないような環境では、主体的な行動をより多く引き出すことは難しいかもしれません。「挑戦することそのものが重要視される」「発言を尊重しあう」という安心・安全な環境をつくることが大切です。
同時に、社員の自律性を適切に評価できるように、社内の評価基準の見直しを行うことも効果的です。例えば、与えられた仕事の達成度や成果だけを評価の対象としてしまうと、指示通りに動く人が高い評価を得ることになり、自律型人材を評価しにくくなってしまいます。成果だけに着目するのではなく、主体性や独自性、チャレンジに対しても正当に評価する仕組みを整えることを心掛けましょう。
3)研修・実践の場を設ける
自律型人材を自社内で定義し、育成しやすい環境を整えても、それが社員に伝わっていなければ意味がありません。企業を取り巻く環境や経営戦略と、自律型人材の必要性への理解を促すにあたっては、研修と実践の場を用意することをおすすめします。
併せて、育成対象となる社員だけではなく、管理職や教育担当者に向けた研修も必要になります。なぜ自社に自律型人材が必要なのか、自律型人材の育成が自社の成長にどのようにつながるのかという認識を一致させておきましょう。
キャリア研修については、下記の記事をご覧ください。
キャリア研修とは?目的と、実際に計画し実施するための方法とは
4)定期的にフィードバックの場を設ける
研修や実践と併せて、定期的なフィードバックの場を設けましょう。フィードバックを繰り返し、目指すべき方向性とのすり合わせを行うことで、効率的な人材育成が可能になります。
社員の悩みやキャリア上の課題は、年代によっても変化していくため、継続的に必要なフィードバックを行うことが重要です。
キャリア面談については、下記の記事をご覧ください。
キャリア面談とは?目的や進め方、成功のためのポイントを解説
6.自律型人材を育成するメリット
自律型人材を育成すると、企業にとってどのようなメリットがあるのでしょうか。主なメリットは下記のとおりです。
1)環境変化にもスピーディーに対応できる
自律型人材が活躍する企業は、さまざまな環境変化にスピーディーに対応できる傾向があります。自律型人材は、自ら考え行動できるため、「指示待ちのために業務が進まない」ということは起こりにくいといえます。たとえイレギュラーな状況でも、自分で改善方法を考え、必要に応じて周囲に働きかけながらスピード感を持って業務を進めることができるでしょう。
2)新たな発想が生まれやすくなる
自律型人材を育成することで、提案が活発化しやすくなります。異なる経験・スキルを持つ社員が、それぞれの視点を活かして意見やアイディアを自由に発信できる環境が整えば、これまでにない新たな発想や解決策、アプローチが次々と生まれることも期待できます。
変化が激しいビジネス環境においては、既存のやり方を続けるだけでは企業の成長は望めません。自律型人材の柔軟な考えや行動が、急激な環境変化にも対応できる組織づくりを後押しするでしょう。
3)管理職の負担軽減ができる
自律型人材の育成は、管理職の負担軽減にもつながります。上司の指示を待たずに主体的に行動する人材が増えれば、部下の指導や育成にかける時間も短縮されるでしょう。管理職は、細かい指示や確認作業の時間が少なくなる分、事業発展に向けた検討など、より重要度の高い仕事に集中できるようになります。
7.自律型人材を育成する難しさ
自律型人材を育成することには企業にとっていくつもメリットがあります。一方で、自律型人材の育成が課題となっている企業もあります。自律型人材の育成メリットと併せて、下記のような難しさについても確認しておきましょう。
1)決定権が上層部に集中する組織体制
自律型人材を育成するには、個々の社員に自身の業務における意思決定権を与え、主体的な判断を促すことが大切です。しかし、決定権が上層部に集中している組織では、業務の遂行にあたって上層部の意向が優先されるため、自律性や柔軟性が削がれてしまいます。
そのような場合は、ある程度の決定権を現場に移行するなど、組織での権限移譲を見直す必要があるでしょう。
2)変革に対する抵抗が強い企業文化
企業として自律型人材を育成したいと考えていても、管理職を含めた社員が前例や既存のやり方に固執し、変革に対して抵抗を示す場合があります。また、「指示がないと不安」「自分の判断が間違っていたらどうしよう」と戸惑う社員も多いかもしれません。
既存の取り組みを重視する傾向が強い場合、変化を拒む空気が生まれやすくなります。変革することによってどのようなメリットがあるのか、変革しなければどのようなリスクがあるのかを明確に伝え、変革しようとする人やチームを称えるなど、ステップを追って組織のマインドを醸成していくことも重要です。
3)業務上のルールやプロセスが煩雑
企業によっては、業務進行上のルールやプロセスが多く、それが社員の自主的な判断や行動を阻害してしまうケースも少なくありません。業務プロセスが細分化され、一つひとつに指示や報告が必要になると、柔軟な判断を行うことは難しくなるでしょう。定型化している非効率な業務を見直すと同時に、社員が主体的に行動できるように、定められたルール内で社員に意思決定の権限を与えるなどの改善が必要です。
4)固定的な評価基準や成果主義による人事評価制度
企業の人事評価制度が、年功序列のような固定的な評価基準だったり、成果主義で目標の達成度や業績などの定量的な数字ばかりを評価されたりすると、自律型人材はなかなか育ちにくいかもしれません。
社員の主体的な行動を促すには、「成果だけではなく、自律的な行動やチャレンジしたことが評価される」と社内で認識されている必要があります。評価基準や人事制度を見直すことも、チャレンジを推奨する企業文化を根付かせる上で重要です。
5)管理職の理解不足
自律型人材の育成にあたっては、管理職の理解を深めることが不可欠です。管理職が理解不足だと、部下の行動を過剰に管理したり、仕事を適切に任せなかったりするなど、自律型人材とは逆の指示待ちの姿勢を生み出してしまいます。自律型人材を育成する際には、対象となる社員だけではなく、管理職に向けても研修を行う必要があるでしょう。
8.自律型人材の育成にもつながるキャリア自律促進の事例
自律型人材を育成する上で重要なポイントになるのが、キャリア自律の促進です。ここからは、株式会社ライフワークスが行った、自律型人材の育成にもつながるキャリア自律促進の事例をご紹介します。
1)「キャリア自律調査」で本質的な課題を把握
自律型人材を育成するためには、キャリア自律の支援が重要です。社員のキャリア自律状況を数値で把握し、本質的な課題を捉えた上で最適な施策を講じるステップを踏んでいくのもひとつの方法でしょう。
社員のキャリア自律度合いは、年代や部署などによってもさまざまであることがあります。キャリア自律度合いの傾向や、そこに影響する要素を把握したい場合は、株式会社ライフワークスが提供する「キャリア自律調査」が有効です。
一人ひとりの「仕事の充実感」「キャリアの展望」「職場での居場所感」「組織コミットメント」を数値で明確にし、キャリア自律の度合いがこの4項目にどのような影響を与えているのか把握します。さらに、キャリア自律度合いに対しての「個人的要因」「環境的要因」「阻害要因」を把握することで、企業内の問題のボトルネックを発見します。例えば、若手社員の離職といった特定の層に課題がある場合は、その要因の把握に活用することも可能です。
ジェーシービー従業員組合様で行った「キャリア自律調査」の調査結果を見てみましょう。
| 組織名 | ジェーシービー従業員組合 |
|---|---|
| 目的 | 約3,500名の組合員が多様で自律的なキャリア形成ができることを目指し「キャリア自律調査」をオンラインで実施。キャリアの支援体制を強化する前に本質的な課題を把握したい。 |
・調査結果
1.「自己理解・前向きな態度」は全体的に高い
2.「職業的自己イメージの明確さ・主体的キャリア形成意識」は低い
3.「組織的キャリア支援」の度合いがキャリア自律(意識・行動)を高め、さらなるコミットメントと、職場の満足度に影響を与えることが判明
・効果
調査結果から、組合のキャリア支援の方針や施策が、組合員の抱えているキャリア課題と合致していることを客観的な事実として示せた。それにより組合のキャリア支援の「軸」が強固になり、これから個々の施策の企画を進めるにあたっても、判断がしやすくなった。さらに、組合員にも施策の根拠をデータで示すことで理解促進につながった。
ジェーシービー従業員組合様の事例については、下記の記事をご覧ください。
多様で自律的なキャリア開発支援に取り組む従業員組合が、「キャリア自律調査」を実施
キャリア自律調査については、下記のページをご覧ください。
キャリア開発 仕組・体制構築支援サービス キャリア自律調査
2)キャリア越境学習プログラムで「行動変容」につなげる
社員が現在のキャリアに滞留し日常業務にマンネリ化が生じ、新しいアイディア・工夫が生まれにくい場合に有効なのが、株式会社ライフワークスが提供する「キャリア越境学習プログラム」です。所属している職場と別の環境を往還(行き来)しながら、業務に関するさまざまな内容を学習、内省します。
下記は、ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社様で行った「キャリア越境学習プログラム」の事例です。
| 組織名 | ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社 |
|---|---|
| 目的 | 社員の「視野の拡大」「自己のポータブルスキルの発見」「ダイバーシティの実践」「スモールビジネスの経営に触れることによる『視座の向上』」 |
| 概要 | 30~40代対象の年代別研修参加者から希望者を募り実施。多様な人材と協働できるプロジェクトに参画するなど社員が実際に往還できる環境を提供。 |
・結果
「これまで受けた研修で最も面白かった」「変化し続けていくことの必要性とさらなる貢献意識の高まりを得られた」「上下関係や決まった役割がないなかでの活動で『シェアードリーダーシップ』(自らの強みを活かしつつ組織の成果の最大化に貢献すること)が発揮できた」など社員から高評価が得られた。
参加者の多くにキャリアオーナーシップの向上が見られたことが最大の効果であった。
キャリア越境学習プログラムについては、下記のページをご覧ください。
キャリア開発 仕組・体制構築支援サービス キャリア越境学習プログラム
9.自律型人材の育成には支援サービスの活用もおすすめ
変化が大きい時代での企業活動にとって、自律型人材の育成と自律型人材が活躍できる組織づくりが重要です。自律型人材を育成できると、組織の成長力が向上する可能性も高いといえるでしょう。
自律型人材とキャリア自律は意味が異なりますが、自律型人材の育成を促進するにあたり、キャリア自律の促進は有効な取り組みのひとつです。
株式会社ライフワークスでは、自社のキャリア自律促進に関わる方に向けて、さまざまなソリューションを提供しています。事例でご紹介した「キャリア自律研修」「キャリア越境学習プログラム」もそのひとつです。一人ひとりがキャリアを考えることは、スキルや知識・経験を身に付け、成長することとも強く結びついています。そうした意味で、人材育成を検討する際に参考になる資料も提供していますので、社員のキャリア自律に課題を持つ方は、ぜひお問い合わせください。
この記事の編集担当

黄瀬 真理
大学卒業後、システム開発に関わった後、人材業界で転職支援、企業向けキャリア開発支援などに幅広く関わる。複業、ワーケーションなど、時間や場所に捉われない働き方を自らも実践中。
国家資格キャリアコンサルタント/ プロティアン・キャリア協会広報アンバサダー / 人的資本経営リーダー認証者/ management3.0受講認定
talentbook:https://www.talent-book.jp/lifeworks/stories/49055
Twitter:https://twitter.com/RussiaRikugame
Linkedin:https://www.linkedin.com/in/marikinose/